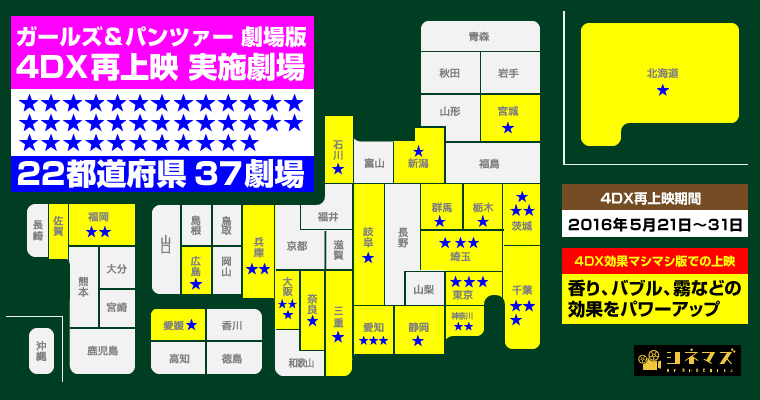(C)SION PRODUCTION 2016
今から25年前の1990年に書き下ろされた脚本を、25年後の今、ついに園監督自身が映画化した作品であり、彼のあふれる程の想いが詰まった作品、それがこの「ひそひそ星」だ。
今週末から劇場公開される話題のこの作品を、今回は一足お先に鑑賞して来ました。
ストーリー
度重なる災害と失敗の末、機械が宇宙を支配し、人工知能を持ったロボットが全体の8割、人間は2割になっている世界。すでに宇宙全体で人間は、滅びてゆく絶滅種と認定されている。
主人公のアンドロイド・鈴木洋子は、宇宙船レンタルナンバーZに乗り込み、相棒のコンピューターきかい6・7・マーMと共に、星々を巡り人間の荷物を届ける宇宙宅配便の配達員をしている。
人間に届ける荷物は、帽子、えんぴつ、洋服など。とさほど重要に見えるものはない。配達には何年もの年月がかかるのだが、マシンである洋子には、なぜ人間が物体をどんな距離にでも瞬時に移動できるテレポーテーションがある時代に、数年もの時間をかけて物を届けるのか理解ができない。洋子は“距離と時間に対する憧れは、人間にとって心臓のときめきのようなものだろう“と、推測している。
洋子は様々な星に降り立ち、かつて人々でにぎわった街や海辺に荷物をとどけていく。荷物を受け取る人々の反応は様々だが、誰もがとても大切そうに、荷物をひきとっていく。30デシベル以上の音をたてると人間が死ぬおそれがあるという“ひそひそ星”では、人間は影絵のような存在だ。洋子は注意深く音をたてないように、ある女性に配達をするのだが・・・。
全編モノクロで撮影された本作において、登場人物のセリフは極限まで少なく、大声で感情を吐露することも無い。そう、全てが淡々と、まるでいつもの日常を追うように進んでいく。
主演の神楽坂恵は、本作で14年間も、ただ一人で淡々と単調な仕事を繰り返してきた主人公を見事に演じており、過去の園子温映画とは全く違った魅力を見せてくれている。彼女は今回ある設定によって、殆ど感情的な芝居を封印されているのだが、逆にそれが本作成功の要因になっていると感じた。
モノクロの画面、限られたセットの空間、タイトル通り「ひそひそ声」で話されるセリフ、にも関わらず、この映画全体から感じる「豊かさ」や「優しさ」は何だろう?
SF映画という、無機質で固く冷たいイメージを持たれがちなジャンルに、人と人との繋がり・思い出の記憶という要素を取り入れた本作は、ここ数年の園子温監督作品とは全く系統の違う、真の園子温映画と呼ぶに相応しい傑作となっている。

(C)SION PRODUCTION 2016
SFのSは、園子温のS。では、SFのFとは?
そう、本作は園子温監督による、紛れも無いSF映画だ。
しかし、「近未来SF映画」、「宇宙船」、「ロボット」、それらの単語から想像されるイメージと観客の先入観は、早くも映画の冒頭10分でひっくり返されることになる。
しかも、それが単にトリッキーなのではなく、むしろ「ああ、そうだよな」という感じ。空想と現実との絶妙な距離感とでも言おうか、リアルに共感できる感じが非常に心地いい。
技術が進んで生活が便利になればなる程、あえて昔の生活やスタイルを懐かしく感じたり、レトロな不便さに新たな価値を見出したりすることは、だれでも思い当たる点があるだろう。例えば、最新機種のiphoneのカバーケースに、木製のものや漆塗りのものを選ぶとか、部屋のインテリアとして昔の電話や家電製品を選んだりするとか。
本作に登場するテープレコーダーや、昔の真空管ラジオ型のコンピューター、動力源としての電池、水道の蛇口から水が出たり、ガスコンロでお湯を沸かすなどの描写。未来的な設定と昔の品物とが合わさると、どうしてもミスマッチ感が強くなりそうなものだが、本作では逆にそこにリアルな生活感が生まれ、むしろ豊かなSFマインドを感じさせる結果となっている。
そう、SFのFは本来フィクションであるが、同時に本作のロケーションとしてその背景に映し出されるのは、驚くべきことに現実の震災被災地=ファクトなのだ。
実際、本作で登場人物のセリフ以上に雄弁に語るのが、今回ロケーションとして撮影された被災地、「福島県・浪江町」の現状。そして、実際に現地で震災の被害にあわれた方や、今も仮設住宅に住む方々が出演されているという点だろう。
スクリーンにモノクロで映し出される、廃墟と化した町並みの数々。正直、被災地の現状が、人間が殆ど絶滅しかけている世界の舞台として描かれて何の違和感もないどころか、むしろリアルに感じられることに、心底ゾッとした。
監督自身の言葉によれば、「福島県・浪江町の、本来は一般の人が入れない地区で撮影をしていた」とのこと。
なにしろ、主人公が途中立ち寄った惑星で出会う人間(ミュージシャンの遠藤賢司が演じる)が、自転車で走る道路の両脇には、なんと陸に打ち上げられたままの漁船が、何隻も放置されたままになっているのだから、監督の言うとおり、「今の日本では通らない企画であり、そのため自主映画として撮った作品」という経緯も納得できるだろう。

(C)SION PRODUCTION 2016
本作こそ、園子温版「2001年魔女の宅急便」!
技術の進歩とテレポーテーションにより、距離と時間に対する憧れが失われ、人間の感情が次第に退廃していった世界。
本作では、「テレポーテーションが可能な世界」という設定でありながら、「あえて長年かけて手渡しで物を送る」という行為が描かれている。
長年配達物の中身を知らずに送り届けていた主人公が、人々と触れ合う内に次第に人間に興味を持ち、ある日配達物の中身を空けて中の品物を見てしまう。そこに込められた記憶の重みは、きっと送り主の人それぞれで違うのだろう。
たとえムダで非効率的な行いでも、人間にはそういう手段でしか伝えられない想いが存在するのだ、そう語られることで、思い出の重みに対して釣り合うだけの手間と時間をかけて届けたい、という人間の思いやりや心は、たとえどんな状況下でも失われないことが描かれていく。
主人公が、種の滅亡を待つかのように細々と生き続ける人々や、荒廃した星でもなお普段の生活を続ける人々の元に届ける品物の数々。実はこれらは、実際に震災の被災地で発見された物であり、亡くなられた人々の遺品も混ざっているそうだ。
宇宙船にコンピューターと二人で生活しながら、人々の想いと大事な贈り物を届け続ける主人公。そう、まさにこれこそ園子温監督による、「2001年魔女の宅急便」だと言えるのではないだろうか。(注:これはあくまでも個人の見解です。念のため)
タイトルである「ひそひそ星」の意味は、ラストに訪れる「ある星」の描写で語られるのだが、それはまさに、未だに大っぴらには発言しにくい福島の現状を表しているかのようだ。
本編中に登場する、音量を計る機械の存在やそのデザイン、ひそひそ声での会話などから、本作での「音の大きさ」=「放射能量」のメタファーとして考えると、タイトルの「ひそひそ星」の持つ重みがさらに理解出来るのではないかと思う。
最後に
映画が始まって30分後に、主人公が降り立った惑星の荒廃した土地を、一人歩く場面がある。正直、セリフも無く主人公がただ歩くだけの場面を、これほど面白いと感じた映画は久しぶりだった。
映画の中で印象的に繰り返される、潰れた空き缶と靴の描写。靴底に挟まったままの潰れた空き缶は、そのまま「被災地」のメタファーであり、靴底にくっついたままで音を立てながらどこまでも離れないでいる潰れた空き缶、それこそは、何年たっても拭い去れない震災の記憶と見ることが出来るだろう。
本作は確かにSF映画として作られているが、その主人公は「福島県・浪江町」の町そのものだと言える。
未だに震災当時の爪あとを残したままの被災地を舞台に、全ての日常が淡々と語られて行くこの映画。SF映画の形を借りた本作に込められた真のテーマ性に気付く頃には、あなたはきっと、もう一度改めて見たくなっているはずだ。
(文:滝口アキラ)