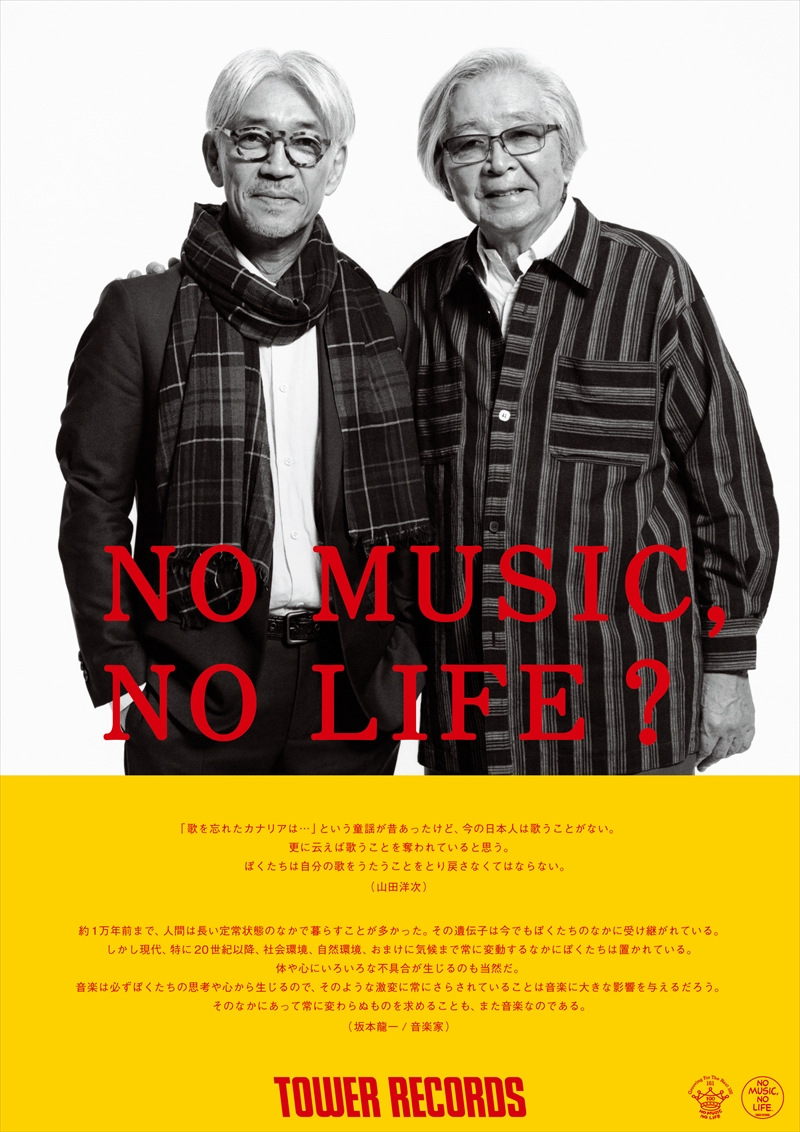深まる秋にふさわしい日本映画をご紹介、その第2弾は……。
《キネマニア共和国~レインボー通りの映画街 vol.62》
小栗康平監督、10年ぶりの新作となる『FOUJITA』です。

ふたつの時代、ふたつの国を通して文化の相違を描出
小栗康平監督といえば、81年に『泥の河』でデビューして以来、『伽倻子のために』(84)『死の棘』(90)『眠る男』(96)『埋もれ木』(05)と発表してきた寡作の監督ではありますが、そのずべてが傑作の誉れ高く、またどのように困難な映画制作体制の中でも絶対に自我を貫き通す厳しい作風で有名な名匠でもあります。
そんな小栗監督が久々に挑んだ新作映画の題材に選んだのが、藤田嗣治。
1920年代のパリで描いた絵画「裸婦像」などが絶賛されて時代の寵児となるも、太平洋戦争中は日本に帰国し、戦争協力画を描き続けて日本美術界の重鎮となり、しかし戦後は戦争責任を問われて再びフランスへ渡り、二度と日本の土を踏むことのなかった画家の人生を通して、ふたつの時代、そしてふたつの文化の違いなどを日仏合作スタイルで描いたものです。
もっとも、ここで小栗監督はTVスペシャルもののような伝記映画になることを徹底的に拒絶し、歴史的事実やその流れなどを説明することも一切なく、ただひたすらフジタの日常そのものを映し出していくことで、1920年代フランスと1940年代日本、ふたつの時代におけるふたつの国の文化の違いを明確に描出していきます。
そのため、藤田嗣治に関して、多少の下調べをしておかないと、何が何だかわからないといった批判も耳にしますが、下調べなんて、今ここに書いておいた彼の人生の大まかな歩みだけ知っておけば十分だと私自身は思います。
むしろ、小栗映画をずっと見続けてきた立場としては、これほど明快な小栗映画も珍しい。

芸術もまた娯楽=エンタテインメントの範疇である
2時間強の上映時間の中、前半はパリでの狂乱が魅惑的に、後半は日本の暗澹たる運命が、はっきり区分けして描かれていくことで、身の置き場所を違えるだけで人はこうも運命が変えられていくものかといった感慨に囚われていきます。
なぜフジタはパリへ行ったのか、なぜ日本に戻って軍部に協力して戦争画を描いたのか、そういった説明も一切ありません。
従って、戦争協力者としてフジタを扱うことによって、反戦映画としてのあからさまなメッセージを打ち出すことも一切ありません。
それを不親切と呼ぶのは簡単ですが、映画とは究極のところ理屈ではなく、映像のうねりに身を委ねることで初めて感じられるものの中にこそ真実があるもので、今回の『FOUJITA』はまさに好例であると同時に、そこには作り手の傲慢さどころか、観客の意識の向上を信じて疑わない作家の祈りみたいなものまで感じられます。
何もかもナレーションや台詞で説明し、わかりやすい構成、わかりやすい編集など、そういった映画も決して否定はしませんし、それゆえの人気作も多々あります。
しかし、だからといって説明のない映画を「説明してないから駄目だ」と批判するのは、それこそ見る側の傲慢であり怠慢ではないでしょうか。
真のエンタテインメントとは、見る側の意識を啓蒙し、向上させるものであると私自身は思っています。
その意味では『FOUJITA』は実によくできたエンタテインメントです。

そもそも芸術映画と娯楽映画を分けること自体がナンセンスで、私自身は芸術もまた娯楽=エンタテインメントの範疇の一つと考えています。
つまり、今回の『FOUJITA』も“芸術”という名のエンタテインメントであり、仮に難解であったとしたら、ならばその難解さを楽しめばいい(『2001年宇宙の旅』を一度見て理解できる人ってこの世に何人います?)。
また、こういったアーティスティックな作品は、賛否も含めて見る側を啓蒙しながら、映画などの鑑賞眼を養わせる糧としても絶好であると思っております。
映画が好きだと自負する人ならば、おそらくはなにがしかの感触を体験できることでしょう。
テレビ局映画も、漫画原作ものも、アニメも特撮ものも、ハリウッド大作も、アーティスティックな作品も、等しくエンタテインメント映画である。
そう考えて接すれば、全ての映画は等しく見どころのある作品となり得るはずです。
小栗映画の中にうかがえるファンタスティック映画としての情緒
小栗監督は『泥の河』以前、TV特撮ヒーロー・シリーズ『流星人間ゾーン』(73)に助監督として就き、21話と26話(最終回)の演出を担当していますが、当時の過酷な現場体制などを批判しつつも、そこでの本多猪四郎監督ら先達と交流を自身の糧としています。
また大林宣彦監督の商業映画デビュー作でもあるカルト・ホラー映画『HOUSE』(77)では助監督として就いています。
そして、よくよく彼の作品群を見ますと、『FOUJITA』も含めて映像のあちこちに独特のファンタスティックな描出がうかがえます。
小栗監督が映画監督デビューしてからの題材そのものにファンタジーは一切ありませんが(ただし『埋もれ木』にはファンタジーと呼びたくなるほどの情緒が充満しています)、その描出、たとえば『FOUJITA』でもパリの路地などの捉え方は実にファンタスティックで、そもそも『流星人間ゾーン』のときから彼は路地裏などを好んで撮っていますが、そういった経験から培ってきた自身の資質が、いつしか題材的ジャンルの別を超えて、映画そのものをファンタスティックな情緒のものとして映えさせているのだと私は思います。
これは、ロシアの名匠アンドレイ・タルコフスキーも全く同じで、とかくシネフィルのエリート意識を満たしているかのような難解な芸術映画の作り手こそ、実は映画をファンタスティックな域にまで高めることに長けた達人であることに気づきさえすれば、全ての映画に難解なものなどないことも理解できるのではないでしょうか。
『FOUJITA』では、特に前半、パリの狂騒描写に小栗映画ならではのファンタスティックな情緒が見事にあふれています。花魁行列の再現シーンなど、描出そのものによってフジタの人間像がうかがえて来ますし、対する日本でのシーンのどんどん暗くなっていく映像と、最後の最後でカタルシスをもたらすような一瞬の画と音の炸裂にも目を見張らされます。
考えずに感じることでたどり着ける究極のエンタテインメント映画

思えばフジタを演じるオダギリジョーも、ここではおかっぱ頭にロイド眼鏡にちょび髭と、形からフジタという役に入っているようで、それがまず視覚に訴える映画の演技としてのツボにピタリ収まっているように感じられました。
私たち観客は、二つの時代と場所におけるフジタの日常を通して、文化の違いなどを痛感するとともに、映画を見る行為そのものの愉しさを満喫できます。それが小栗康平監督の『FOUJITA』であると確信しています。
こういう映画を見るたびに『燃えよドラゴン』のブルース・リーの名セリフ「考えるな、感じろ」が脳裏をよぎります。
全ての映画を理屈で考えず、目と耳で感じることができるようになったときこそ、映画というメディアは芸術という縛りから解放されるのかもしれません。
少なくとも私にとって『FOUJITA』をはじめとするすべての小栗映画は、究極のエンタテインメント映画なのです。
(文:増當竜也)