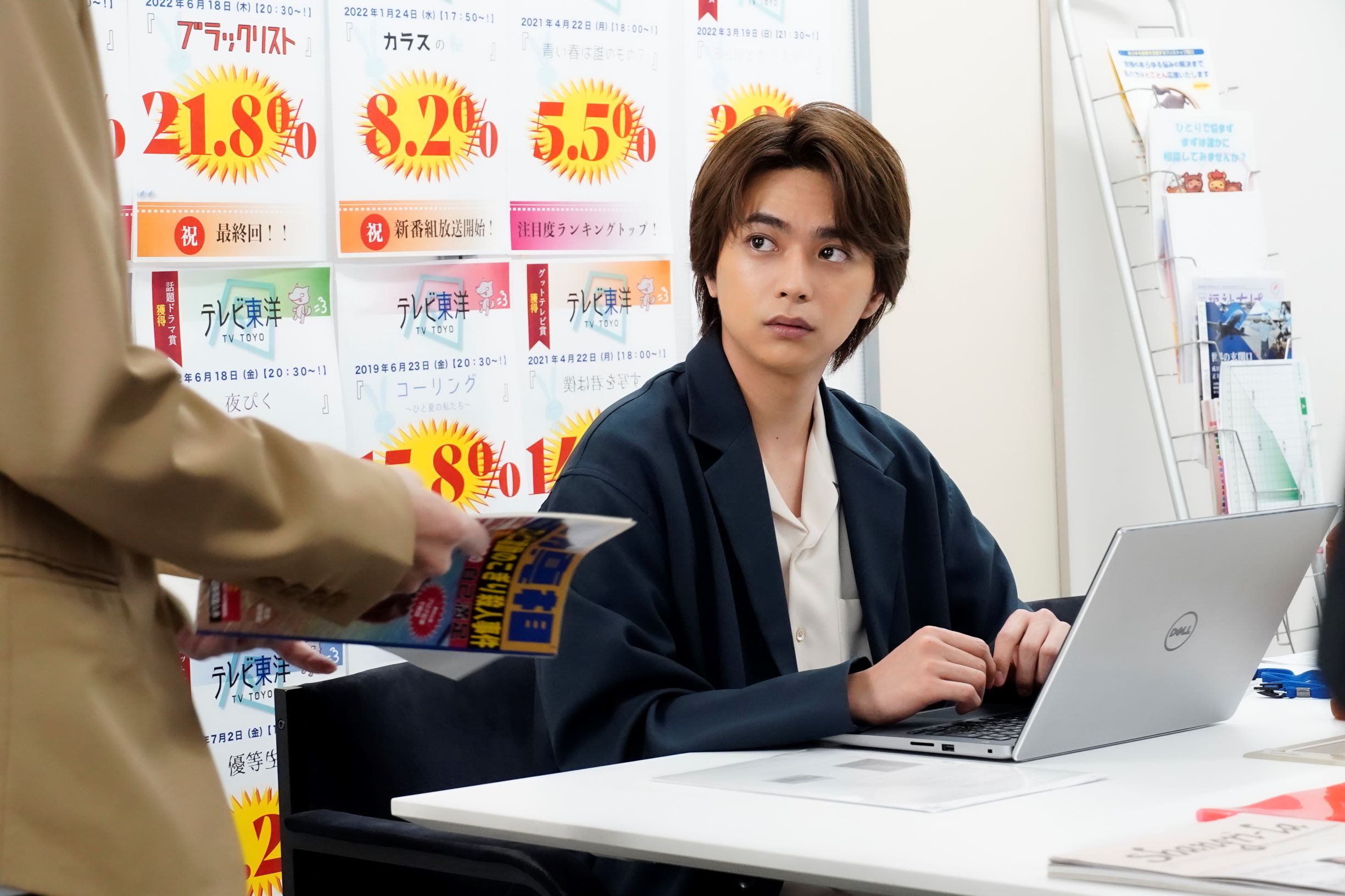撮影は一年以上前。久々に顔を合わせたはずの二人は、実に自然な距離感で穏やかに笑い合っていた。無理することのない笑顔と会話が、そのまま映画『あの娘は知らない』で演じた奈々と俊太郎に重なって映る。
井樫彩監督が脚本も手がけた本作において、福地桃子と岡山天音は初共演を果たした。お互いに大切な人を亡くした喪失感を共有する二人を演じながら、何に思いを馳せていたのだろうか。
何よりも、現場で得られる感覚を頼りに

©LesPros entertainment
――本作『あの娘は知らない』は、福地さん演じる奈々と、岡山さん演じる俊太郎の“喪失と再生”の物語です。家族を亡くした奈々が切り盛りする民宿へ、恋人を亡くした俊太郎が訪れることによって始まります。
福地桃子(以下、福地):今回、私が演じた奈々は当て書きしてもらった役柄です。それにともなって、脚本完成前の時点から井樫監督とお話をさせてもらいました。当て書きだからといって、決して簡単だったわけではありません。自分のどんな部分が投影されているのか想像しつつも、まったく予想外な脚本でした。
岡山天音(以下、岡山):物語のすべてが脚本に落とし込まれているわけではない、と僕は感じたんです。答えが書き切られているわけではない、というか。具体を提示しない、抽象的で、まるで詩のような脚本だと思いました。なかなか「これはこうだな」とすぐに結論を出せるような種類の映画じゃなかったよね。

©LesPros entertainment
福地:そうですね。準備してはいくのですが、現場で受け取った感情から奈々の人柄を膨らませていく……そんな過程が多かったかもしれません。監督からは「奈々のセリフだけど、福地さんの言葉でもあるからね」と言われていました。自分のなかから出てくるものを大切にすること、それを手がかりにしながら演じていた気がします。
岡山:現場で得られる感覚を頼りにしながらお芝居をしていたのは、僕も一緒ですね。その場に俊太郎として立っている、そんな実感がいちばん大事なのかな、と。僕が演じた俊太郎 って、いつもポケットに最低限の持ち物を⼊れてフラフラと街を歩いているようなキャラ クターなんです。なので、撮影では映らない場⾯でも、ポケットのなかに携帯やタバコを⼊ れていました。そういうことが⼤切な現場だという気がしたんです。

©LesPros entertainment
福地:現場で時間を過ごしていくうちに、奈々としての生活が自分に馴染んでいくような感覚でした。天音さん演じる俊太郎さんとの会話が重ねられるにつれ、どんどんキャラクターが染みついてくるような。ロケ地である静岡や初島の、その場にある空気や波の音や虫の声、そういった要素が身体に入ってくるのを感じるごとに、奈々として自然にその場に“居られる”ような気がしたんです。
――同じく大切な人を亡くした経験のある方にとっては、感じるものの多い映画になったのでは?
岡山:実際には、大切な人や物を失ってはいないけど、何かを喪失したような心地になることって、あると思っていて。僕自身、身近な人を亡くした過去もなければ、お葬式に出席した経験もありません。でも、自分のなかから大切な何かが消えてしまったような“心の色”を覚えることはある。恋人を亡くした俊太郎と同じ、痛みのようなものを。奈々や俊太郎と同じ経験をしていなくとも、喪失やそれにともなう傷をなぞるような、自分の“いつかの瞬間”を思い出すような作品になってるんじゃないか。そんな風に思います。
ロケ地・静岡や初島への思い

©LesPros entertainment
――本作は静岡県の伊東や初島で撮影されていて、美しい景色も魅力のひとつとなっています。お二人にとって、思い入れのあるシーンは?
岡山:奈々さんと俊太郎が、初めて一緒にタバコを吸った防波堤が、冒頭に出てくるんですけど。あそこ、とってもムードがあってフォトジェニックで、大好きな場所ですね。
福地:素敵な場所ですよね。風の通りがすごくよかった気がします。
岡山:そうだ、なかなかタバコの火が点かなかったんだよね。
福地:自然と前に進みたくなるような場所だなと感じたので、私もよく覚えています。

©LesPros entertainment
――撮影から公開まで期間が経つと、作品を俯瞰して見られるものでしょうか?
岡山:まったく客観的にはなれないですね。もしかしたら、時間の問題じゃないのかもしれません。撮影そのものが、体験としてものすごく濃かったので。あれからだいぶ時間が経って薄れていることもあるけれど、こうやって話しているうちに鮮明に思い出すこともあるような、そんな作品ですね。
福地:私も、完成した映像を観てから気づくことがありました。その反対に、お芝居をしながら肌で感じたものが、そのままスクリーンに残っていて感動したりもして。「このシーン好きだな」「やっぱり温もりを感じるシーンだな」と、改めて味わい直すことも多かったですね。これから観てくださる皆さまにも届く映画になるといいな、と思います。
(撮影=Marco Perboni/取材・文=北村有)
–{『あの娘は知らない』作品情報}–
■『あの娘は知らない』作品情報
9月23日(金)より新宿武蔵野館ほか、全国順次公開。
幼くして家族を亡くした奈々は、海辺の町で旅館を営んで暮らしていた。そんな奈々の前に、恋人を失った俊太郎が現れる。2人は俊太郎の恋人の足跡を求めて、ともに町を彷徨いはじめる。それぞれの痛みを抱えた2人が紡ぐ、喪失と再生の物語。
出演
福地桃子 岡山天音
野崎智子 吉田大駕 赤瀬一紀 丸林孝太郎 上野凱
諏訪太朗 久保田磨希
安藤玉恵
脚本・監督
井樫彩
製作
レプロエンタテインメント 東放学園映画専門学校
配給
アーク・フィルムズ レプロエンタテインメント