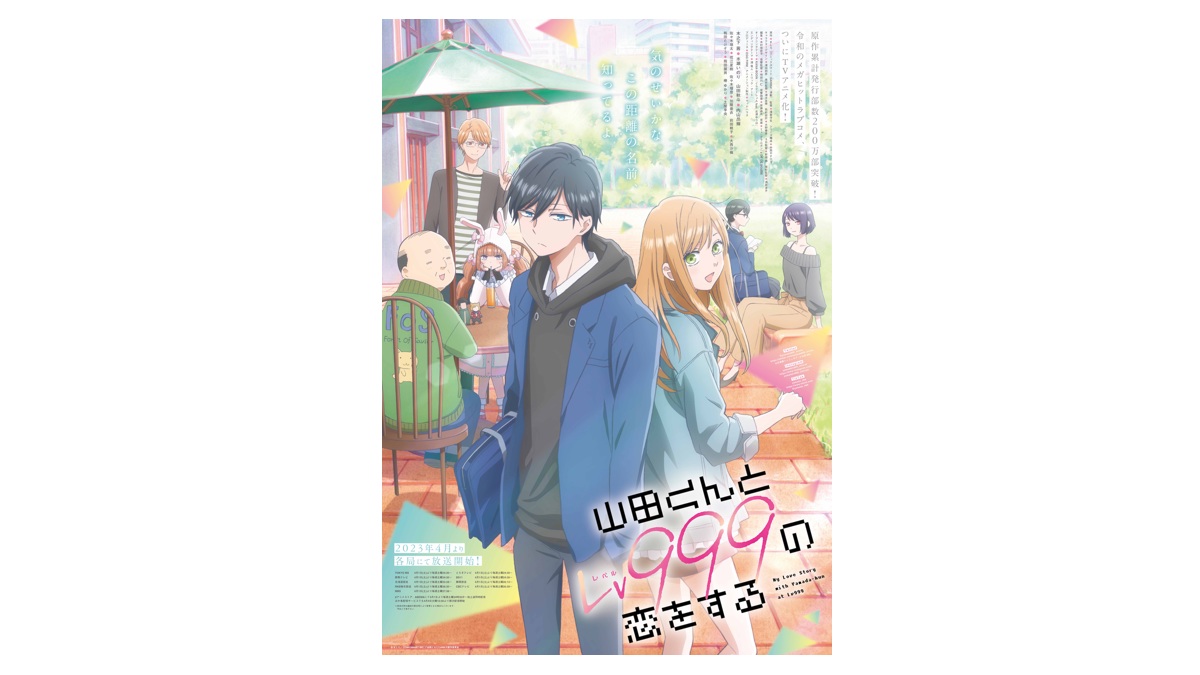毎週火曜よる10時にNHKドラマ10枠にて放送中の「大奥」が3月14日、ついに最終回を迎える。
本作は、よしながふみによる累計発行部数600万部超えの人気同名漫画を原作としたもの。若い男子のみが感染する奇病によって男性の人口が女性の4分の1にまで減少した江戸パラレルワールドを舞台に、美男三千人が女将軍を囲む“男女逆転の大奥”を描いている。
今回は最終回を前に名言・名場面とともに、原作のメッセージ性をさらに強めた「大奥」の素晴らしさを振り返っていきたい。
[※本記事は広告リンクを含みます。]
三代将軍家光・万里小路有功編
【あらすじ】
若い男子のみが感染し、致死率80%に及ぶ奇病「赤面疱瘡」が蔓延した頃、三代将軍家光が死亡。乳母である春日局(斉藤由貴)は家光の死を隠すために、その血を唯一引く娘・千恵(堀田真由)に性別を偽らせ、身代わりとして生活させる。さらに、春日局は彼女に跡継ぎを産ませるべく、美しき僧・万里小路有功(福士蒼汰)を騙して大奥に連れてくるのだった。
1. 二羽の傷つき凍えた雛たちによる恋の始まり
家光×有功編における最高の名場面と言っても過言ではないのが、女装した有功が自身の打掛を知恵に羽織らせる場面。「上様のほうがよほどお似合いにございます」と打掛を羽織らせた後、有功は「千恵様」と優しく語りかける。
この有功の行いが女性としての人生を奪われながらも、子を産むという役目だけ残された千恵の凍りついた心を溶かしたのだ。堰を切ったように溢れる堀田真由の涙、慈愛に満ちた優しい福士蒼汰の表情は号泣必至。
原作ではこの場面に「それは二羽の傷付き凍えた雛が互いに身を寄せ合うように始まった恋であった」というモノローグが添えられている。ドラマでは「凍え雛 一羽身を寄せ 坊主雛 千の恵や 功有らんと願ふ」というオリジナルの和歌を有功に読ませた。
直前にあった和歌でも詠んで上様の心を掴めと春日局が有功に命ずる、これまたオリジナルの展開も効いている。有功が和歌を詠んだのは、千恵にお褥を共にしてもらうためじゃない。心を通わせるためだ。ここは自分たちにも心があることを、二人が春日局に示した場面でもある。
2. 「わしは仏をさらってきたのじゃ」
千恵と有功から大切な人と人生を奪い、多くの人を手にかけてきた春日局。しかし、人の痛みが分からないサイコパスではなく、彼女は彼女なりの正義があることは原作でも描かれていた。
春日局は戦乱の世を生き抜いてきたからこそ、徳川が治める平和な世が続くことを誰より願っている。私たちの感覚からすれば、彼女の行いは悪逆非道も甚だしい。ただ、まだ乱世が終わったばかりで徳川を滅ぼそうとする者がいるかもしれない時代には、彼女のような存在も必要と言えなくもないのだ。
自ら悪役を買って出る春日局を「鬼でもなければ平気なはずはございますまい」と敬ったのが、被害者であるはずの有功。この時、春日局が放った「わしは仏をさらってきたのじゃ」というオリジナルの台詞がすごかった。有功の海よりも深い愛情は誰の心も丸裸にしてしまう。本当に仏のような人だった。
あんなに恐ろしかった春日局もここでは安らかな顔を見せる。まさに鬼にも仏にもなる存在を体現した春日局の名演にも拍手を送りたい。
3. お万好みとされる“流水紋”に込められた願い
有功と千恵の間には子ができず、別の男たちと褥を共にするようになる千恵。嫉妬に苦しむ有功はついに「男と女の恐ろしい業から解き放ってくださりませ」 とお褥すべりを申し出る。
代わりに春日局の死後、ずっと空席だった大奥総取締に就任。大奥の男たちの前で就任の挨拶をするときに有功が羽織っていたのが、“流水紋”の裃(かみしも)だ。流水紋は以降、お万好みの柄として伝わっていくのだが、なぜ有功はこの柄を選んだのか。
原作では、特に理由は語られていなかった。一方のドラマでは脚本家の森下佳子が、嫉妬・羨望・孤独がつきものな大奥において「その思いに寄り添い、渇きを癒し、涙を洗い、時に四季を映し、慰める。水の流れのようにここにありたい」という“流水紋”に込められた思いを有功に語らせる。なんて素敵な解釈なのだろう。
少しでもこの大奥で人間らしく生きていけるように。有功の願いや使命は後世にも受け継がれていくこととなる。
–{五代将軍綱吉・右衛門佐編}–
五代将軍綱吉・右衛門佐編
【あらすじ】
時は流れ、五代将軍綱吉(仲里依紗)の時代。大奥だけに留まらず、城の外でも男を漁る奔放な性格の綱吉は市中で“当代一の色狂い”と噂される。そんな中でも綱吉との間に子を持てずにいた御台は京から大奥中が噂をするほどの美青年である公家出身の右衛門佐(山本耕史)を呼び寄せるのだが、これがまた曲者で……。
4. 「そうか、これは辱めであったか!」
序盤から濡れ場が多めだった綱吉×右衛門佐編。とはいっても、ただ単に話題を集めるために過激なシーンを何度も入れ込んだわけじゃない。いや、むしろ濡れ場が多いという理由で、興味本位にのぞいてきた人に伝えたかったのだと思う。「性的な場面や自分の身体を他人に見られることが、いかに人間の心に負担をかけるか」ということを。
娘を失い、悲しみに暮れている時も、月のものがなくなった以降でさえも世継ぎを生むという使命を父・桂昌院(竜雷太)に強要され続けた綱吉。その心はどんどん蝕まれていき、彼女は大奥の男二人に自分の目の前でまぐわうことを強要する。
それを右衛門佐に「人前で睦み合えというのは辱めにございましょう!」と咎められた際に、綱吉が放つのが「そうか、これは辱めであったか!」というドラマオリジナルの台詞。そして、続けて綱吉は「どうであった、私の夜の営みは」と問う。これは彼女が男たちと睦み合う場面を見てきた私たちにも向けられた問いだ。
この時に仲里依紗が見せた、鬼気迫る演技も目が離せないほどに素晴らしかった。インティマシー・コーディネーターを入れた演出、森下脚本の名台詞、仲の名演技が融合し、多くの人の心を揺さぶったのだ。
5. 「みな上様に恋をしているのでござります」
右衛門佐は綱吉と褥を共にする男たちにいつも「大奥の男たちはみな、上様に恋をしているのでござります」という台詞を言わせていた。その理由を聞き、みんな一瞬にして右衛門佐に心を奪われたことだろう。
桂昌院にまで曲者と言わしめた彼は、自分の力を試すために大奥にやってきた。綱吉の夜伽の相手ではなく大奥総取締の座に就いたのも、もう種馬扱いされたくなかったから。だけど、実はひと目見た時から綱吉に恋い焦がれていたのである。綱吉も右衛門佐に惹かれていたが、搾取され続けてきた二人だからこそ、誰よりも慎重だ。
長きにわたる駆け引きの末に二人が結ばれたのは、互いに生殖という役目から解放された後のこと。その時ようやく、右衛門佐は綱吉に本当の思いを告げる。「上様に恋をしておりましたよ」と。そう、彼はずっと自分の言えない思いを綱吉と褥を共にする男たちに代わりに言わせていたのだ。
この時の無邪気に喜ぶ綱吉の表情がとても愛おしかった。そんな綱吉を抱きしめながら、涙を流し、幸せを噛みしめる右衛門佐も。二人の幸せな時間はほんの一瞬であれど、私たちに大きな幸福感をもたらしてくれた。
6. 「佐には会えましたか?」
かたや原作以上に、綱吉への重すぎる愛を持て余した柳沢吉保を演じた倉科カナ。桂昌院とのシーンは双方ねっとりとした演技を披露し、昼ドラ感が半端なかった。美しく妖艶で何を考えているか一切わからない。そのくせ、綱吉に対する恋心は見え見えだった吉保。
しかし側用人である彼女が綱吉に想いを告げることは叶わない。ただ、そばにいるために綱吉の父である桂昌院の手綱を握っておいたのだろう。
そんな吉保の思いが溢れ出てしまうのが、綱吉編のラストシーン。寝所で「右衛門佐だけが欲得のない慈しみを教えてくれた」と語る綱吉の顔に吉保は濡れ布巾をかぶせ、殺害へ至る。悲痛な面持ちで「私のどこに欲得がございましたでしょうか」と問いかける吉保は恐ろしくも切なかった。彼女もずっと何の見返りもなく、綱吉に尽くしてきたのだから。
バッドエンドとも言えるが、最後の「佐には会えましたか?」という吉保の台詞と表情が圧巻だった。この一言で、吉保は綱吉を楽にして、右衛門佐のもとに送ってあげたのかもしれないという希望も持たせてくれる。
–{八代将軍吉宗・水野祐之進編}–
八代将軍吉宗・水野祐之進編
【あらすじ】
貧乏な旗本の息子・水野祐之進(中島裕翔)は、身分違いな幼馴染との結婚を諦めるために大奥入り。その頃、就任したばかりの八代将軍吉宗(冨永愛)に夜伽相手として選ばれるが……。のちに吉宗は側用人の加納久通(貫地谷しほり)らと共に赤面疱瘡撲滅に動く。
7. 「今日からそなたは私の男じゃ」
最終回までの全9話を振り返ってみると、本作は初回の放送からしっかりと視聴者の心を掌握していた。もちろん脚本の素晴らしさもあるが、第一に冨永愛が演じる吉宗の完成度が想像以上の出来だったからだ。
慎ましやかな掻取(かいどり)をピシッと着こなした冨永が御鈴廊下の入り口に立った時、「この実写化は成功だな」と誰もが思ったに違いない。時代劇初挑戦ではあるが、乗馬や殺陣を習っていたこと、また日本の歴史にも精通している冨永は説得力をもって女将軍・吉宗をこのドラマに存在させた。
また原作をただなぞるだけではなく、冨永ならではの吉宗になっていたことも多くの人の心を掴んだ理由であろう。冨永が演じる吉宗は原作よりもさらにチャーミングで親しみやすさがある。特に水野と夜伽を共にするシーンでは恋する乙女のような表情も見せており、とても愛らしかった。
だが、その後に「今日からそなたは私の男じゃ」と水野に迫る場面には、同性でありながら心がときめいたのを覚えている。
8. 大奥総取締・藤波の説法が深い
原作ファンの間で、この時代の大奥総取締・藤波に対して良いイメージを持っている人はあまりいないだろう。手に負えないほどの悪役ではないが、欲に塗れた男という印象が強い。特段大きな見せ場はないはずだが、やはり片岡愛之助をキャスティングしただけあって、しっかりとドラマでは見せ場を作っていた。
とにかく吉宗や久通に「総触れはまだかまだか」とうるさい藤波。だが、そこまで頻繁に大奥の男たちと吉宗を会わそうとするのにはちゃんと理由があったのだ。その理由が分かったのは、吉宗が宿下がりを自ら申し出た藤波に暇金を渡す場面。この時に暇金を受け取る片岡の所作がそれはそれは美しいのだが、対する吉宗はとにかく事務的で情緒がない。そんな吉宗に藤波が最後に厳しくも愛のある説法を披露する。
「ここにおる者達は皆、上様の種馬にございます。けれど、それをあからさまにしてはあまりにも虚し過ぎる。故にあたかも情の通ったものに彩ってきたのが、ここ大奥にございます」
ここで、有功が大奥総取締に就任した時の言葉が活きてくる。同胞たちの苦しみを少しでも和らげる存在でありたいという有功の願いを、藤波もまた受け継いでいたのだ。最後の最後で大奥総取締としての矜持を見せつけられ、一気に藤波の株が急上昇した。
9. 吉宗と家重の抱擁
たったの数カ月でドラマ史に残る名シーンを数多く生み出した「大奥」。そして極め付きとして、観た人が絶対に忘れられない感動の場面を届けた。それが吉宗と、その娘である家重の抱擁だ。
言語・排尿障害を患っており、自分が思うように身体を動かせなかったり、伝えたいことを上手く伝えられなかったりする家重。その難役を見事にこなしたのが三浦透子だ。決して褒められたわけではない行動の中に光る家重の聡明さや、その胸の内に抱えるもどかしさを表出させた。
「役立たずだから死にたい」という家重の苦しみに触れた時、吉宗はそこにある本当の願いに気づく。それは「生きるなら人の役に立ちたい」という願い。人に理解されにくいだけで、久通の言う将軍に最も大事な“他の者を思う心”を家重はきちんと持っていたのだ。
吉宗が家重の将軍としての器に気づくまでの展開もお見事であったが、吉宗と家重の思いが溢れんばかりの抱擁が胸を大きく揺さぶる。母親に認めてもらえた安心と喜び、娘の苦しみにこれまで気づけなかったことへの申し訳なさと未来を託す気持ち。双方の思いに泣けた。
こうして振り返ってみると、改めて思う。NHKドラマ10「大奥」は脚本・演出・演技の3拍子揃った名作であったと。どれ一つ取っても欠けているところがない。
最終回もきっと涙なしには見られない名言・名場面を届けてくれることだろう。
(文:苫とり子)
「大奥」作品情報
放送予定
2023年1月10日(火)放送スタート (NHK総合)毎週火曜 よる10時~10時45分
※初回は15分拡大
出演
3代 徳川家光(堀田真由) × 万里小路有功(福士蒼汰)
5代 徳川綱吉(仲里依紗) × 右衛門佐(山本耕史)
8代 徳川吉宗(冨永愛) × 水野祐之進(中島裕翔)
原作
よしながふみ「大奥」
脚本
森下佳子
制作統括
藤並英樹
プロデューサー
舩田遼介
松田恭
演出
大原拓 田島彰洋 川野秀昭