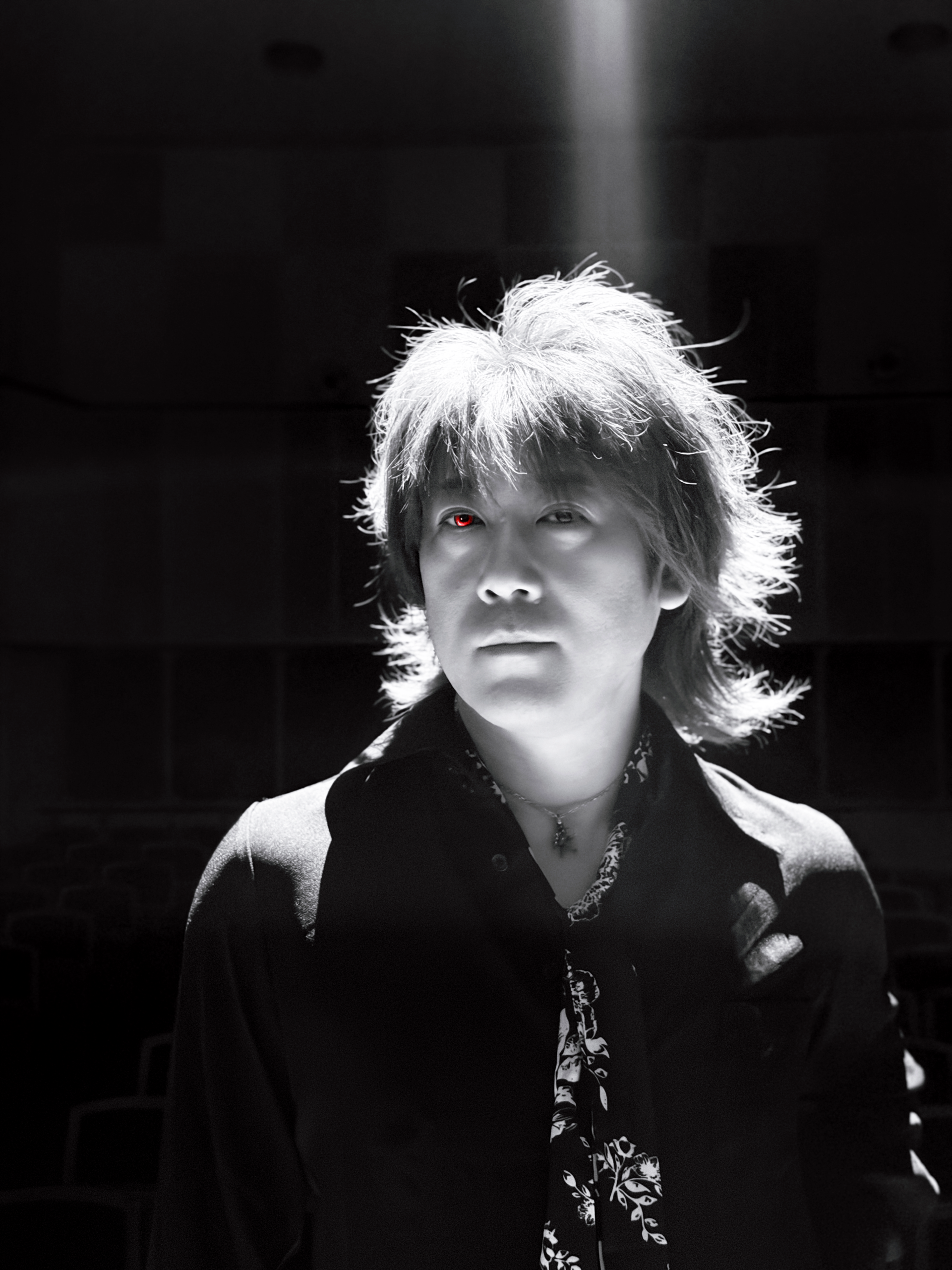金曜の夜に欲しいのは、理屈より先に“血が騒ぐ”一本。
香港の雑踏で拳が鳴り、浅草の舞台で言葉が火花を散らす――松竹が70年代に放った二作には、ジャンルを越えて同じ匂いがある。
相棒と、見世物。
強敵を追いかける執念/相棒を手放さない意地。
今夜の気分を変えるなら、この公開年順でいこう。
『少林寺拳法 ムサシ香港に現わる』(1976)――“強敵”に取り憑かれた男、香港へ

少林寺拳法の達人・山中ムサシ(風間健)は、より強い相手を求めて世界をさすらい、ついに拳法の本場・香港へ辿り着く。
ところが到着早々、九竜地区の裏通りで白人の大男に襲われ、反射的に“叩き殺して”しまう。
この噂は香港中に広がり、拳法に理解のある趙延年(馮毅)のもとへ招かれる。
その夜、趙の邸宅を訪ねたムサシは、襲来してきた一団の中に“超人のような動き”の男を目撃する。
名は呉宗憲。
趙の命を狙い、夜半に現れては襲うという。
ムサシの胸に、消えない火が灯る――呉と対決したい。
以降、物語はこの一点に、容赦なく吸い寄せられていく。
そこへ「日本から流れて来た」という柴田玲子が近づく。
綺麗な瞳に心が動き、マカオへデートに出かけるが、玲子はなぜか趙のことをしつこく尋ねる。
甘さと不穏が同居する気配が、ムサシの“真っ直ぐすぎる執念”をいっそう危うく照らす。
やがて趙の墓参りの日、呉の一味が襲来。ムサシはついに、呉との対決へ――。
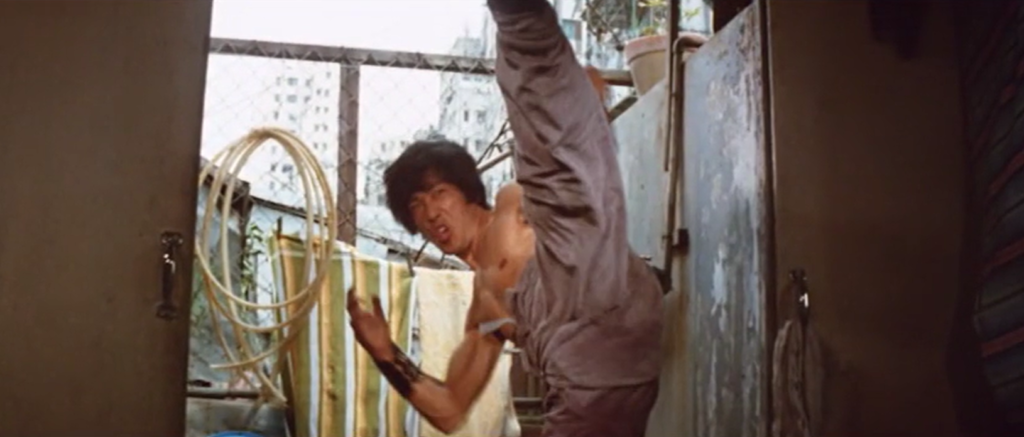
見どころ
- 一直線の快感:「強い奴とやりたい」だけで進む男の物語。
だから拳の一撃が、余計に重い。 - “香港”の体温:修業譚というより、雑踏と路地の匂いごと飲み込む現場映画。
- 松竹らしさの意外性:喜劇のイメージに寄りかからず、空手アクションを真正面から撮りにいく潔さ。
作品データ
- 公開:1976年11月27日/上映時間:85分
- 監督:南部英夫/脚本:猪又憲吾・長尾啓司・南部英夫
- 原案:風間健・三村晴彦/撮影:竹村博/音楽:鏑木創
- 出演:風間健、干洋、五十嵐淳子、孟秋 ほか/配給:松竹/©1976松竹株式会社
『喜劇役者たち・九八(クーパー)とゲイブル』(1978)――笑いが“芸”になり、やがて“祈り”になる
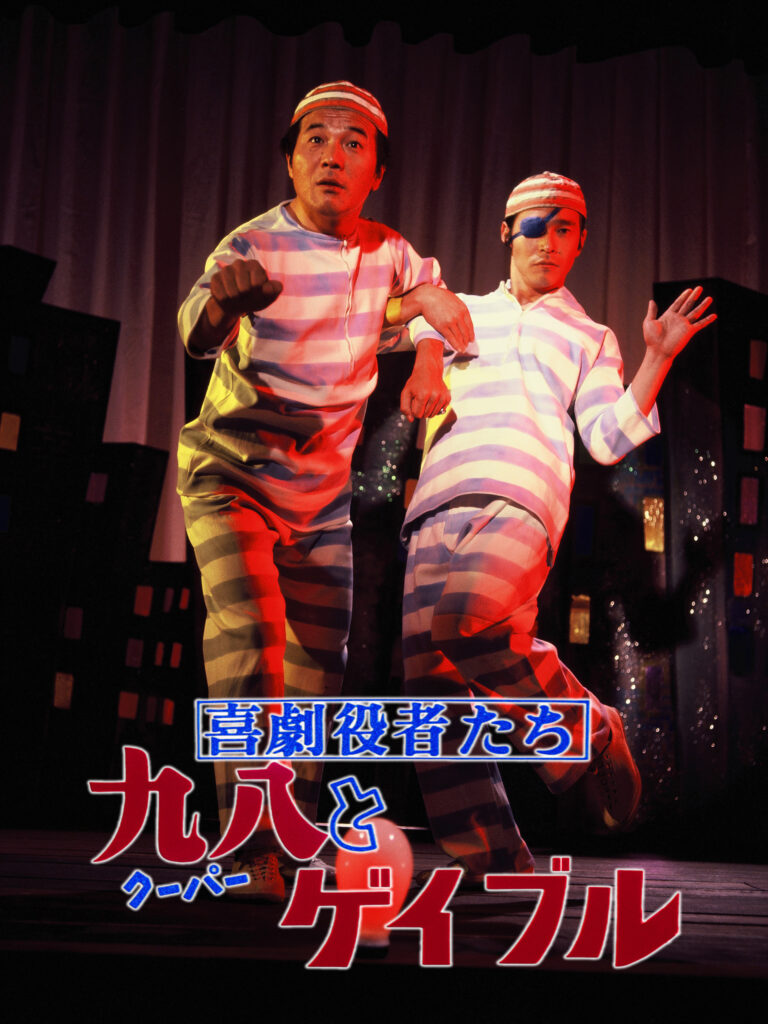
喜劇役者・港金一(通称:芸利九八=愛川欽也)は、一旗あげようと踊り子ラビアンローズ(園佳也子)についてドサ廻り。
ある晩、北京放送から英語放送、さらには花モゲラ語まで操る奇妙な男・苦楽芸振(タモリ)と出会う。
妙にウマが合った金一は、彼を相棒にして浅草へ連れ帰る。
ストリップ小屋の支配人・松井(笑福亭鶴光)の計らいで、ストリップの合間にコントをやることになった二人は、観客の人気を得る。
張込み中の刑事の前で、コントに見せかけて現場をかき回し、ストリッパーを救い出す場面など、“笑いの瞬発力”がそのままドラマを押し出す。
だが、この映画が忘れがたいのは、笑いが順調に勝ち続けないからだ。
舞台を観ていた村岡(三木のり平)から告げられるのは、芸振が道化症で病院に入院していた過去。
注目が集まり始めた頃、婦人議員団の視察の場で芸振は突如かみつき始め、病状の悪化が露わになる。
救急車が呼ばれるなか、金一は芸振を連れて逃げ出す。
「芸人なんて所詮、まともな人間なんかじゃない」――金一が自分に言い聞かせるように吐き出す言葉が、胸の奥に刺さる。
病か、芸か。才能か、呪いか。
相棒を“分身”として抱え込むラストは、成功譚よりずっと切実で、ずっと人間臭い。

見どころ
- 原作・井上ひさしの“喜劇の刃”:成り上がりの軽さの裏で、社会の顔色がじわじわ変わっていく。
- 愛川欽也×タモリの相棒熱:芸で生きる者同士の、寄り添いと依存が同時に走る。
- 浅草という舞台:喝采も転落も、同じ距離で見える場所。
見世物の最前線で“芸”は鍛えられ、削られる。
作品データ
- 公開:1978年3月21日/上映時間:93分
- 監督:瀬川昌治/原作:井上ひさし/脚本:田坂啓
- 撮影:丸山恵司/音楽:いずみたく
- 出演:愛川欽也、タモリ、秋野太作、佐藤オリエ ほか/配給:松竹/©1978松竹株式会社
まとめ――拳か、言葉か。どちらも“相棒”が人生を決める
『ムサシ香港』は、強敵への執念が男を前へ前へ押し出す映画だ。
迷いを削ぎ落とし、最後に残るのは“闘う理由”そのもの。
『九八とゲイブル』は、笑いの眩しさの裏で、相棒を抱え込む切実さが沁みてくる映画だ。
拍手が止まっても、舞台裏で人生は続いていく。
金曜の夜にこの二本を並べる意味は、はっきりしている。
拳でしか証明できないものと、言葉でしか救えないもの――その両方を、たった数時間で往復できるからだ。
まずは香港へ。次に浅草へ。
観終わった頃には、週末の体温が一段上がっている。
配信サービス一覧
『少林寺拳法 ムサシ香港に現わる』(1976)
・U-NEXT
・Hulu
・Amazon Prime Video
・YouTube
・Lemino
・FOD
・ひかりTV
・J:COM
・TELASA
・AppleTV
『喜劇役者たち・九八(クーパー)とゲイブル』(1978)
・U-NEXT
・Hulu
・Amazon Prime Video
・YouTube
・Lemino
・J:COM
・ひかりTV
・TELASA
・AppleTV